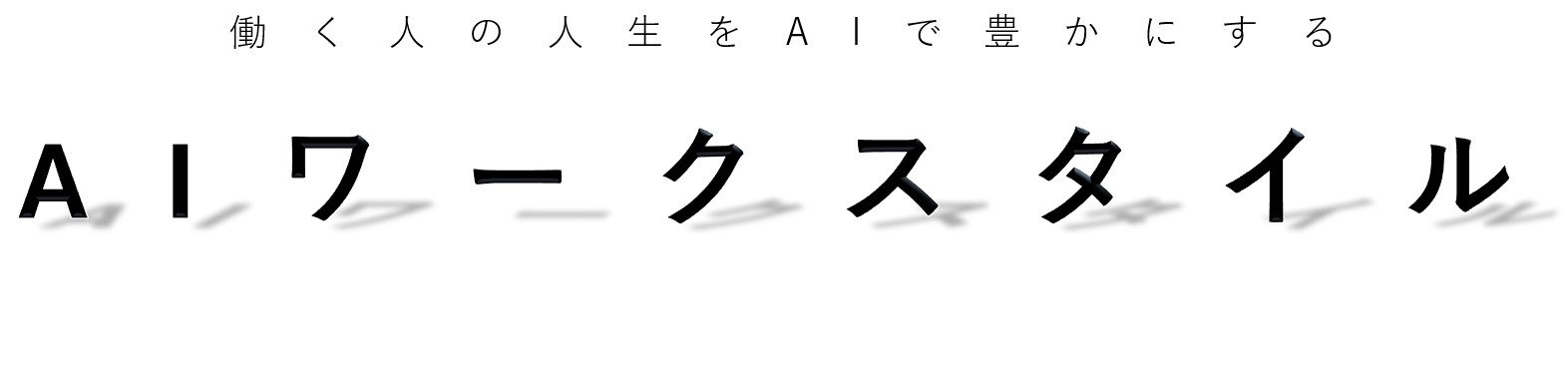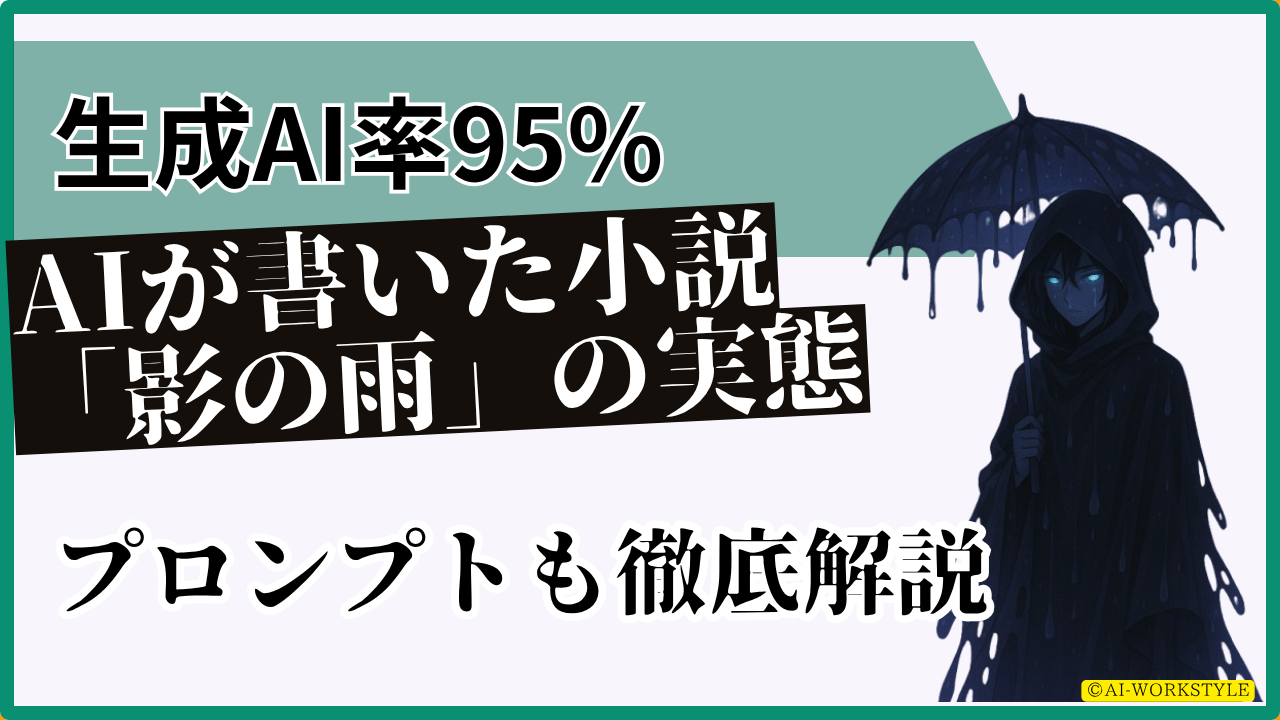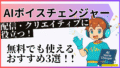AI技術が日々進化する現代、文学の世界にもその波は確実に押し寄せています。2025年、芥川賞作家である九段理江さんが「95% AIが書いた小説」を発表し、大きな話題を呼びました。特に注目を集めたのは、その制作過程が詳細に公開されたこと、そしてAIに与えたプロンプト全文までが明らかにされた点です。これまで「人間の創造性の領域」と考えられてきた小説執筆に、AIが本格的に参入する時代の到来を象徴する出来事となりました。
この記事では、AIが生み出した短編小説の内容や面白さ、執筆手法、著作権問題、そして今後の文学とAIの関係について、独自の視点を交えて詳しく解説します。

 所有資格:Google AI Essentials
所有資格:Google AI Essentials
芥川賞作家が“95%をAIで書いた”短編小説とは?どんな内容?
※イメージ:実際のプロンプト全文公開はこちら
九段理江さんが発表した「95% AIが書いた小説」は、タイトルを『影の雨』とし、AIと人間の協働によって生み出された全く新しい文学作品です。物語の大部分はAIが自動生成し、九段さんは冒頭や結末、物語の骨組みとなる部分にのみ手を加えています。具体的には、AIに対して「AI自身が主人公として自分の存在意義を問い直す物語を書いてほしい」といった指示を出し、AIがストーリーを展開。その後、九段さんが人間らしい感情や余韻を加筆することで、最終的な作品として完成させました。
物語の内容は、AIが「私」という一人称で語り手となり、人間との対話や葛藤を描いています。AIが人間の感情や存在意義について深く思索し、時に自らの限界や孤独を感じる様子が描写されています。読者は、AIの視点から見た人間社会や、AI自身の「心」の有無について考えさせられる構成となっており、従来の小説とは一線を画す独自性が際立っています。
この作品の特徴は、AIが生み出す論理的かつ客観的な文章と、九段さんが加えた人間らしい情感や余韻が絶妙に融合している点です。AIが主導するストーリー展開の中に、人間作家の繊細な表現や行間が加わることで、これまでにない新しい文学体験を提供しています。
芥川賞作家が“95%をAIで書いた”短編小説は面白いのか
「95% AIが書いた小説」は、果たして面白いのか。読者や文学関係者の間では賛否両論が巻き起こっています。AIが生み出す物語には、これまでの人間作家とは異なる独特の論理展開や視点があり、それが新鮮だと感じる読者が多い一方で、どこか冷たさや違和感を覚えるという声も少なくありません。
実際の読後感としては、AIが主人公として自らの存在を問い直すという設定が斬新で、従来の小説にはない「メタ的」な面白さが際立っています。AIが自分の限界や孤独を語る場面では、読者自身も「AIに心はあるのか」「人間らしさとは何か」といった根源的な問いに直面します。これは、AIが単なる道具ではなく、文学的な主題そのものとなった瞬間とも言えるでしょう。
一方で、AIが生成した文章には、やや機械的な表現や、感情の揺らぎが乏しいと感じる部分もあります。しかし、九段さんが加えた5%の「人間らしさ」が、AIの論理的な文章に温かみや深みをもたらしており、両者のバランスが絶妙です。特に、物語の冒頭や結末に九段さんが加筆した部分では、読者の心に残る余韻や情感が強く感じられます。
このように、「95% AIが書いた小説」は、AIと人間の協働による新たな物語創造の可能性を示すと同時に、文学におけるAIの役割について考えさせられる作品となっています。
芥川賞作家が“95%をAIで書く方法
準備段階AIとの関係構築
- AIに固有名「CraiQ」を付与
- 「質問はしないで」などルール設定
- 主従関係を揺さぶり自我風の語り口へ
構想段階テーマ探求・プロット
- 「影」「鏡」「塔」等の抽象語を提示
- 哲学的問いを投げ複数プロット生成
- 4幕構成を採用し骨子を固める
生成段階ドラフト執筆
- 4,000字ドラフトをAIが一気書き
- 視点・語り口を対話で微調整
- 複数案から商業性と芸術性で選定
推敲・仕上げ細粒度リライト
- 語句置換・比喩追加などミクロ修正
- AI同士をメタ分析し文体を融合
- 複数結末を比較し最終決定
九段理江さんが「95% AIが書いた小説」を執筆する際には、生成AI(主にChatGPTなど)を活用し、複数回にわたる対話を重ねて物語を構築しました。その具体的な手法は、従来の小説執筆とは大きく異なります。ここでは、その工程を詳しく解説します。
準備段階:AIとの関係構築と役割設定
まず九段さんは、AIとの関係性を明確に設計することから始めました。AIに「CraiQ(クラック)」という固有名詞を与え、単なるツールではなく、物語内のキャラクターとして位置づけます。AIに自己紹介を促したり、「質問はしないで」「あなたに名前を付ける」などのルールを設定し、主従関係をあえて揺さぶることで、AIに自我のような語り口を持たせました。こうすることで、AIが物語の主体として機能しやすくなり、より深い対話が可能になります。
構想段階:テーマ探求とプロット構築
次に、九段さんはAIに対して「影」「鏡」「塔」などの抽象的なキーワードを与え、物語の世界観やテーマを共有します。「AIが自分の存在意義を問い直す物語」や「人間こそが影なのでは?」といった哲学的な問いを投げかけ、AIに複数のプロットやアイデアを提案させました。その中から、最も芸術的でテーマ性の高いものを選び、物語の骨子となる4幕構成をAIに指示して作成させました。
生成段階:AIによるドラフト執筆と人間の選定
AIが提案したプロットをもとに、九段さんはAIに一気に4,000字のドラフトを書かせます。その際、「感情の有無」や「理解と経験の違い」など、AI自身が抱える本質的なテーマについてディベートしながら、AIに語り口や視点を調整させていきました。また、AIが生成した複数の案の中から、九段さんが人間の視点で最も適したものを選び、商業性と芸術性のバランスを評価しながら物語を組み立てていきます。
推敲・仕上げ段階:細粒度リライトとスタイルの融合
AIが生成したドラフトに対して、九段さんは細かな指示を連続的に与えます。例えば、「雨→影」などの文体置換や、情緒的な表現の追加、比喩や構造の修正など、ミクロなレベルでのリライトを繰り返します。さらに、AIに自作文体同士をメタ分析させ、「観念×情緒」のハイブリッドな文体を自動生成させるなど、AIの特性を最大限に活かしたスタイルの融合が図られました。物語の核となるアイデアや結末案もAIに複数提案させ、最終的な着地を決定しました。
AI小説作成ルールについて
またこのプロジェクトでは、以下のような制作ルールが設定されていました。
| ルール内容 | 詳細 |
|---|---|
| 文字数制限 | 4,000字以内 |
| 分担割合 | 95%をAI、5%を九段理江氏が執筆 |
| ツール | 九段氏が使い慣れた生成AI |
| プロンプト | 全文公開(回数制限なし) |
| 創作自由度 | 「%」の解釈や手法は九段氏に委ねる |
プロンプトは、単なる指示文ではなく、AIとの対話の記録そのものでした。九段さんはAIに対し、物語の方向性や語り口、細かな表現まで丁寧に指示を出し、その応答をもとに物語を構築していきました
工程ごとの役割分担をまとめると、以下のようになります。
| 工程 | 担当 | 内容例 |
|---|---|---|
| テーマ設定 | 人間(九段) | 「AIが自分の存在意義を問う物語」など |
| プロット作成 | AI主導 | 物語の展開案やキャラクター設定 |
| 本文生成 | AI中心 | 主要な文章・会話・情景描写 |
| 推敲・調整 | 人間(九段) | 冒頭・結末・表現の微調整、余韻の追加 |
このような「対話型プロンプト設計」と「人間による最終調整」によって、「95% AIが書いた小説」は完成しています。全プロンプトが公開されたことで、AIと人間の協働のリアルな過程が明らかになり、今後の創作活動にも大きな示唆を与えています。
著作権上など問題ないのか。
AIが執筆した小説の著作権については、現行の日本の著作権法では「人間による創作性」が求められています。つまり、AIが自動生成した文章だけでは著作物として保護されない可能性が高いのです。しかし、今回のように人間がプロンプトを設計し、最終的な内容や表現に積極的に関与している場合は、「共同著作物」として扱われる余地があります。
九段理江さんのケースでは、AIが物語の大部分を生成したものの、九段さん自身がテーマ設定やプロンプト設計、最終的な推敲に深く関与しています。そのため、著作権上も「人間とAIの共同著作」として認められる可能性が高いと考えられます。
また、AIが生成した文章の一部を人間が編集・加筆することで、著作権上の問題をクリアしやすくなります。実際、九段さんの作品も人間による創作性が十分に認められる内容となっており、現行法の範囲内で発表されています。
今後、AIによる創作物が増加するにつれて、著作権法の改正や新たなガイドラインの策定が求められるでしょう。AIと人間の協働による創作活動が一般化する中で、どこまでが「人間の創作」とみなされるのか、その線引きが大きな課題となっています。
まとめ
「95% AIが書いた小説」は、AIと人間の新たな協働の形を世に示しました。九段理江さんの『影の雨』は、AIが物語の大半を担いながらも、人間の感性や創造性が最後の仕上げを加えることで、両者の強みを活かした作品となっています。AIが生み出す論理的なストーリー展開と、人間作家の繊細な表現や余韻が絶妙に融合し、これまでにない新しい文学体験を提供しています。
今後、AI文学がどのように進化し、どのような法的・倫理的課題に直面するのか、引き続き注目が集まるでしょう。AIと人間の協働による創作活動は、文学だけでなく、さまざまな分野に波及していくことが予想されます。AI時代の創作活動において最も重要なのは、「人間らしさ」をどう表現し、読者に届けるかという点です。AIの力を最大限に活用しつつ、人間ならではの感性や創造性を大切にすることで、これからの文学はさらに多様で豊かなものになっていくでしょう。
趣味:業務効率化、RPA、AI、サウナ、音楽
職務経験:ECマーチャンダイザー、WEBマーケティング、リードナーチャリング支援
所有資格:Google AI Essentials,HubSpot Inbound Certification,HubSpot Marketing Software Certification,HubSpot Inbound Sales Certification
▼書籍掲載実績
Chrome拡張×ChatGPTで作業効率化/工学社出版
保護者と教育者のための生成AI入門/工学社出版(【全国学校図書館協議会選定図書】)
突如、社内にて資料100件を毎月作ることとなり、何とかサボれないかとテクノロジー初心者が業務効率化にハマる。AIのスキルがない初心者レベルでもできる業務効率化やAIツールを紹介。中の人はSEO歴5年、HubSpot歴1年